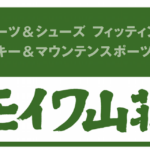おはようございます!
久しぶりのブログ更新となります。
久しぶりの更新で「怒っておく」などのタイトルは憚られますが、幣校の「レッスン料値上げ」にも直結している部分でもありますので、この機会に声を上げていきたいと思います。
と同時に、一人でも多くの方に「声を上げる」ということの大切さと申しますか、政府の政策のままに流されていく「だけ」では本当に日本という国が消えてなくなるかもしれないという危機的状況すら「感じられない」という状況を受け入れてしまうということの重大さに気が付いていただければと思い、口幅ったくお前ごときがといわれると思いますが、思い切ってキーボードに向かいます。
さて、いろいろ書きたいことはあるのですが、我々の生活に直結していて、それでいて「このままではまずいよね」ということがわかりやすい昨今の「ガソリン価格高騰」という部分に的を絞って怒ってみたいと思います。
ガソリン、驚くほど高いですよね。
僕が免許を取ったころなんて、リッター98円という時があって、「お金ないからドライブでもいくか」なんて会話が行き交うくらいにガソリンは安価なものでした。
それがいまはどうでしょう。
倍ですよ。倍。
結論から書きましょう。
ガソリンが高いのではなくて「税金」が高いのです。
ところで、皆様はガソリン価格の「内訳」ってご存じですか?
これね、結構複雑でややこしい(わざとわかりにくくして「もういいや」と思わせようとしているとしか思えません・・・)のですが、とりあえず見ていきましょう。
2023年7月時点で、ガソリンの全国平均は183円でした。(AIのBard調べ)
この価格の「ガソリン本体」と「それにかかる税金」の内訳をみてみましょう。
| 本体価格 | 1リットルあたり112円 |
| 税金 | 1リットルあたり71円 |
このうち、税金の「中身」を見てみましょう。
| ガソリン税(暫定税率25.1円・本則税率28.7円) | 53.8円 |
| 地方揮発油税(本則税率) | 19.3円 |
| 石油石炭税(本則税率) | 1.5円 |
| 温暖化対策税(本則税率) | 2円 |
この「税金の内訳」をみても、これだけの税金がガソリンにはかかっているわけなんです。
で、今度は上の表の中にあります「暫定税率」と「本則税率」ってなに?となると思いますので、次はそこを紐解いていきますね。
・暫定税率
1974年に道路整備の財源不足に対応するため、一時的に増額された税率。その後、期限が定められていた暫定税率ですが、期限後も延長や税率の引き上げが繰り返され、現在も25.1円の税金が課せられています。
・本則税率
ガソリンに本来課せらる税金。この中に「温暖化対策税」として2円も課せられているのは納得できませんが。
このようにして、ガソリンには「巧みに」税金が上乗せされているんですよ。
そしてーーーー!!!
もっとも解せない、許せないのが、ただでさえこれだけの税金が課せられているのにもかかわらず、我々消費者はガソリンを購入するときにさらに税金を課せらているんですよ。
お気づきですよね?
そうですよ。「消費税」ですよ。
これ、長くなるので端的に書きますが、これってまぎれもなく「二重課税」ですからね?
「二重課税」は税制の基本原則として「二重課税の禁止」というものがあり、本来しっかりと議論されて極力二重課税にならないような方向に向かっていくのが健全な方向なのですが(しかしながら国税庁の見解で、必ずしも違法にはならないという見解もありますので、国に訴えて裁判でどうにかなるものではないようです)、しかし、ことガソリンに関してはこれがまかり通っております。
これの納得いかないところはですね、ガソリン税の内の「暫定税率25.1円」というものはですね、1974年に道路整備の財源不足を補うために「一時的」にガソリンに課税したまさに「暫定」の税金でして、いわゆる「道路特定財源」として「特別な財源」であったのですが、平成21年に「特別な財源」という地位がなくなり「一般財源」として扱われるという法律により廃止になっているんですね。
ゆえに、ガソリンに「暫定税率」として課税している根拠はすでにないわけなんです。
なのにいまだに25.1円も課税されているんですよ。
これ、納得できますか?
で、ですよ。さらに続きますよ。
最近になって岸田総理(最近は国内に目を向けるよりも海外への補助金・援助など国外への大盤振る舞いが続いていることから「ばらまきメガネ」と呼ばれいるようです)は「リッター175円を目指してガソリン価格を下げる!」と息まいておりますが、しかもこれを「減税」ではなく「補助金」で賄うとしておりますが、この辺り、何も知らないと「お、総理頑張ってんじゃん」となるわけなんですよ。
で、このカラクリを見破るために、ここで「トリガー条項」という言葉を理解することが必要となってきますので、ここでしっかりとこの「トリガー条項」というものを理解しておきたいと思います。
・トリガー条項
一定の事例が発生した場合に自動的に一定の措置(税率の変更、歳出の削減等)が実施される法律の規定です。
日本では、ガソリン価格の高騰時にガソリン税を減税するトリガー条項が、2010年の税制改正で導入されました。
トリガー条項の具体的な内容は、以下のとおりです。
- レギュラーガソリンの全国平均価格が3か月連続で1リットル160円を超えた場合、ガソリン税の特則税率分の1リットル25.1円を減税する。
- 3か月連続で130円を下回った場合は特則税率を復活する。
この「トリガー条項」は本来「ガソリン価格の高騰による国民の負担を軽減すること」を目的としているのですが、しかし、今はこの「トリガー条項」が機能していないんですよ。
なぜか。
それは2011年の東日本大震災による復興財源を確保するために、ガソリンに課せられている「暫定税率」である「道路特定財源」からの税収を充てるためにこの「トリガー条項」が凍結されていて、「ガソリン価格の高騰による国民の負担を軽減すること」を目的とした「トリガー条項」が機能していないんです。
なので、今は国民民主党の玉木代表などが先陣をきってこの「トリガー条項の凍結の解除」、つまり「トリガー条項を機能させて、暫定税率分の25.1円を減税すればいいじゃん!」ということを必死に与党に訴えているのですが、岸田総理は聞く耳持たず、減税ではなく「補助金」でガソリン価格を抑えようとしているのです。
しかも175円を目標て。
トリガー条項の凍結を解除すれば一気に25.1円も安くなるんですよ。それでも160円台ですがね。
ま、今はサウジアラビアが原油の減産延長に合意したことから原油価格の高騰もあるのであきらめる部分もあるのですが、しかし、減税対策で大幅にガソリン価格を抑えることもできるんです。
もっと言えば、鈴木財務相だったかな?
「トリガー条項の凍結を解除すれば国民のガソリンの買い控えが起こる」
などとトンチンカンな発言をする始末。
は?
ガソリンやすくなって買い控え?
それよりもこのインフレで(てかスタグフレーションだと思ってますけどね)金融緩和継続で円の価値を下げておいて何をぬかしておるのか。
消費税減税ひとつでかなり救われると思うのですがね。
いやだめだ、書きたいこと沸いてきた。
これ以上書くとごちゃごちゃしますので、国民負担率の増加、可処分所得の低下などの問題はまたの機会に書いてみたいと思います。
ガソリン価格の高騰への怒りでございました。